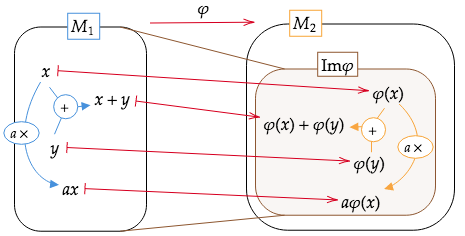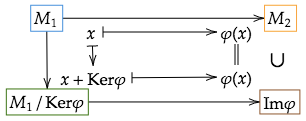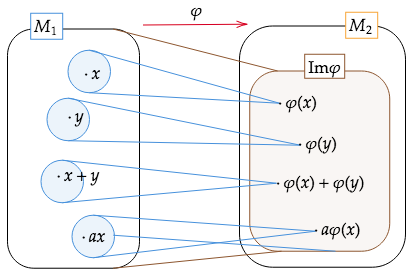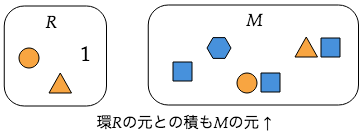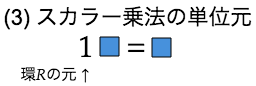かんたんイスクイル(簡単とは言ってない)
もう各Slotごとに詳述するのがめんどくさくなりました。
はじめに(お気持ち)
イスクイル学習、日本語母語話者にとってかなりやりやすいのではないかと思っている。
注意
毎度のことですが、ちゃんと勉強するなら須らく原典を読むべし。
http://www.ithkuil.net/morpho-phonology_v_0_18_5.pdf
この記事は単なる筆者のメモです。
書き終わってからいろいろ足したくなったので気が向いた時に加筆します。
品詞
大きく分けて3つ、formatives(形成詞)とadjuncts(付属詞)とreferentials(参照詞)。
自然言語との対応関係は以下の通り。
- formatives(形成詞):名詞+動詞+分詞
- adjuncts(付属詞):副詞
- referentials(参照詞):代名詞
語順
基本は1番目のformativeが動詞。ただし題目を動詞の前に持ってくることが可能。
特にイスクイル4の場合はアクセント位置で動詞か名詞か分詞か判断できるので3の時よりわかりやすくなった。
動詞以外の語順?イスクイルでは豊富な格変化()で名詞どうしの関係性を理解できるから何でもOK。日本語もそうだよね、わかるね。
formatives(形成詞)の音韻形態論
全部で10スロット(5個も減ったから簡単)。
I: Cc(形容詞かどうか的なやつ)+II: Vv(語義派生)+III: Cr(語根)+IV: Vr(語義派生)+V: CsVx(接辞)+VI: Ca(語義派生)+VII: VxCs(接辞)+VIII: VnCn(法/格スコープ)+IX: Vc/Vf/Vk(格/形式?/法っぽいやつ)+X: [stress](slot IXの意味を定める)
「スロット」なる謎単語が急に出てくるからわかりづらいだけで、本質はセム語の語根子音に母音突っ込んだり接頭辞/接尾辞つけて派生語作ったりするそれ。k1t2b3の1とか2とか3みたいなやつがSlot。ただしイスクイルは省エネなので12k456789みたいな逝かれた構成になっているだけ。「だけ」ではない。やはり逝かれている。
なお、Ccなどは1〜5個の子音連続で構成され、Vvなどは(多分)1〜3個の母音で構成されます。
語根周りの話(辞書定義されている範疇)
各語根に対してstem(語幹、Slot II)、specification(仕様、Slot IV)による単語の派生的意味は辞書的に定義されている。なのでその通りに活用すればいい。
例えば辞書の2.1.4を見るといろいろごちゃごちゃ書いてあります。が、とりあえず-LČŘ-「便所」という語根は-LCW-「建築設備」という語根と同様の活用をするということがわかります。
ここのstem 1-bscのところを見てみると、
「連続的な機械的、電気的、配管的又は生活的な状態を維持し、提供するために、建築物に組み込まれた恒久的な固定具として機能している状態/行為/状態プロセス; そのような器具」みたいなことが書かれています。
ということは、-LČŘ-をstem 1-bscで活用させると「便所」という単語が作れるということ。
つまり「便所」を表す語幹は-alčřa-(最初のaは飛ぶことが結構多い)。
つまらないので別の例も見てみます。stem 2-csvのところでは「設備を利用する人間の行為」みたいなことが書かれています。ということは、-LČŘ-をstem 2-csvで活用させると「うんこする行為」とか「おしっこする行為」とか「排泄行為」という単語が作れる。表の通りに活用すると-elčře-。たまたま母音が被ってしまいましたが、1個目の母音と2個目の母音は一般に異なる音価になります。
辞書定義されていない語根周りの話
version(転換、SlotII)、function(機能、Slot IV)、context(文脈、Slot IV)の3つに関しては特に辞書で意味が規定されているわけではない。が、Slot IIとIVで活用する。
- version(転換):非完結的(processual)か完結的(completive)か、というのに近い?
- function(機能):状態/静態(stative)か動作/動態(dynamic)か
- context(文脈):(イスクイル3と等価なのかわからない)
functionでは状態と動作を区別します。-stem2-LČŘ-csv-「うんこする」で言うと、stative function "-elčře-"は「うんこしている(状態に着目)」、dynamic function "-elčřo-"は「うんこをする(行為に着目)」。
versionに関して。processualは特に目的を達成する意図がない行為。一方でcompletiveは目的完遂に焦点があります。とりあえず「うんこしに行った」のがprocessual、「うんこしに行って結果うんこ出しきった」のがcompletive。
contextは保留。
Ca
configuration+extension+affiliation+perspective+essenceという観点から語義を派生させることができる。というか、それぞれ異なる語彙が生える。
要するに、うんこという行為が複数回行われているとか、うんこ行為が現在から切り離されてるとか、一般的うんこ行為とか、イマジナリー排便とか。
concatenation(連結)
Slot Iをもりもり活用することで形容詞っぽくなるかそうじゃないかが示せる。
タイプ1とタイプ2の2種類(と「連結しない」)がある。
タイプ1はいわゆる形容詞。タイプ2は合成語として新しい概念を形成する。「北極のクマ」(タイプ1)と「北極グマ」(タイプ2)のように、前者は単に「北極にいるクマ」ということしか言わないが、後者は「北極グマ」という新たな概念に言及している。
Slot IX周りの話
Slot IXがVc(名詞の格)かVk(動詞のいろいろ)かどっちになるかはSlot Xに従う。
つまり、stressが後ろから2番目の音節ならVc、最終音節ならVk。後ろから3番目の音節ならVc(分詞?正確に言うとframed relationのcase)。concated formativeの時はVf。
Vc(格)
格は今回68個に減ったのですごく簡単になった(当社比)。
Vk(動詞に関する嬉しい情報たち)
なんかいろいろある。
adjuncts(付属詞)の音韻形態論
なんか知らんがめっちゃ増えた。滅茶苦茶になってるのでちょっとわからない。いやなんでお前ら分裂した?イスクイル3ではひとまとまりだったよね?
- single-affix adjunct:わからん
- multiple-affix adjunct:知らん
- modular adjunct:誰お前
- register adjunct:なんだお前
- carrier adjunct(借用):(イスクイルから見た)借用語を使う時に
- quotative adjucnt(引用):直接話法的に文章を引っ張ってきたい時に
- naming adjunct(名称):固有名詞を呼称する際に?
- phrasal adjunct:謎
referentials(参照詞)の音韻形態論
イスクイル3では代名詞的なやつがadjunctsの範疇にありましたが、イスクイル4では独立。おめでとう。
わからん。